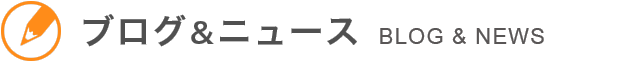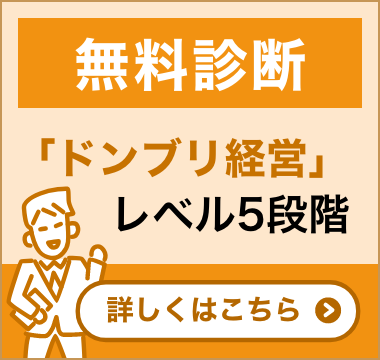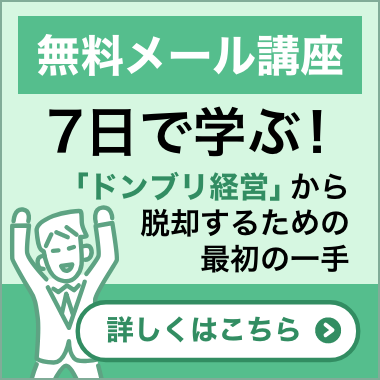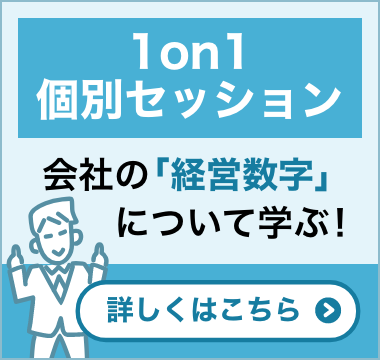2025年10月30日
カテゴリー:
損益計算書の5つの利益を徹底解説|経営判断に欠かせない数字の読み方

365日ブログ
3,013日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
経営者にとって、損益計算書(P/L:Profit and Loss Statement)は会社の経営状態を読み解く最重要資料のひとつです。
しかし、「売上と利益はなんとなく見ているけれど、詳しくは分からない」という経営者も少なくありません。
実は、損益計算書には5つの利益が段階的に示されており、それぞれの意味を理解することで、会社の「儲けの構造」が明確になります。
この記事では、「5つの利益」について、わかりやすく解説します。

1.売上総利益(粗利益)|本業の「儲け力」を表す指標
売上総利益(Gross Profit)は、売上高 − 売上原価で求められます。
たとえば、1,000万円の売上に対して仕入や製造原価が700万円であれば、粗利益は300万円です。
✅ポイント
- ・商品力・仕入交渉力・価格設定力を反映する利益。
- ・粗利率(売上総利益 ÷ 売上高)が低下していないか要チェック。
💡改善策
- ・仕入コストの見直し
- ・高付加価値商品の開発
- ・値引き販売の抑制
2.営業利益|本業の実力を示す利益
営業利益(Operating Profit)は、売上総利益 − 販売費及び一般管理費で算出します。
人件費、家賃、広告宣伝費、交通費など、日常的な経費を差し引いた結果、本業で稼げているかどうかが分かります。
✅ポイント
- ・本業の経営効率を表す「実力値」。
- ・赤字の場合、構造的な問題(コスト過多・売上単価の低さ)を疑うべき。
💡改善策
- ・固定費の削減(人員配置・家賃・サブスク契約など)
- ・生産性の向上
- ・利益率の高いサービスへのシフト
3.経常利益|企業の「安定力」を示す利益
経常利益(Ordinary Profit)は、営業利益 ± 営業外収益・費用で求めます。
たとえば受取利息や支払利息、投資有価証券の配当などが該当します。
✅ポイント
- ・企業の本業+金融活動のトータル収益力を示す。
- ・銀行や金融機関が重視する指標。
💡改善策
- ・借入金の利息負担を軽減(返済計画・借換)
- ・遊休資産の活用
- ・不要な支出(寄付金・雑費など)の見直し
4.税引前当期純利益|税金計算の基礎となる利益
経常利益に、特別利益・特別損失(固定資産売却益や災害損失など)を加減して算出します。
この段階で、税金を計算するための基礎となる「課税前の利益」が明確になります。
✅ポイント
- ・一時的な損益を除いた「本来の稼ぐ力」を見る。
- ・決算調整や節税対策の前に、まずはこの利益を正確に把握。
5.当期純利益|最終的な「会社の儲け」
最終段階の利益が当期純利益(Net Profit)です。
税金を支払った後に手元に残る「純粋な利益」であり、内部留保や将来投資の原資となります。
✅ポイント
- ・継続的に黒字を維持できるかが、企業の持続可能性を左右。
- ・純利益=「会社の未来を作る力」。
損益計算書を経営に活かす3つの実践ステップ
1.毎月の試算表で5つの利益を確認する
→ 税理士や会計担当者に、損益分岐点や利益構造を定期的に確認。- 2.粗利率と営業利益率をKPI化する
→ 経営改善の効果を測るための指標に設定。 - 3.金融機関や投資家に対して信頼性を高める
→ 経常利益・純利益の安定が信用評価に直結。
まとめ:5つの利益を理解すれば「数字で語れる経営者」になれる
損益計算書の5つの利益は、単なる会計用語ではなく、経営の方向性を示す羅針盤です。
それぞれの利益がどう変動しているかを見れば、会社の「健康状態」と「課題」が明確に見えてきます。
経営判断を感覚ではなく数字で行うために、ぜひ月次での確認を習慣化しましょう。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄