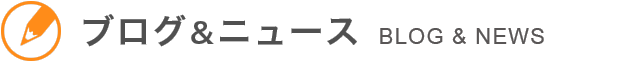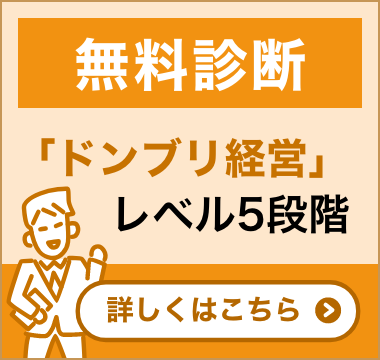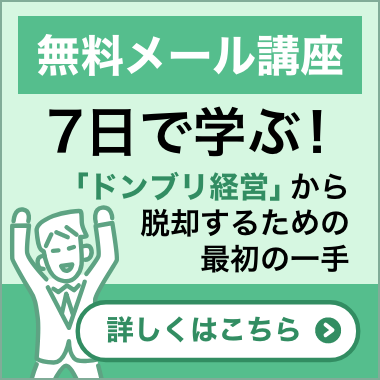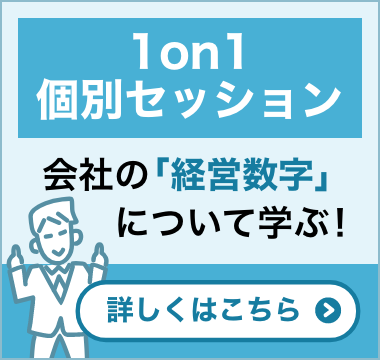2025年10月29日
カテゴリー:
法人化のリスクと留意点|設立コスト・事務負担・社会保険

365日ブログ
3,012日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
ある規模感になれば、
個人事業から法人化を検討する場合あります。
法人化すれば、節税、信用力アップ、組織化…というメリットは確かに魅力です。
しかし、法人化には「こちらも負担・リスク」が伴います。
今回は、設立コスト・事務負担・社会保険という観点から、法人化前に押さえておくべきポイントをお伝えします。
新設法人や新たに法人化を検討している方に向けて、現場の実務視点で整理します。

1. 設立コスト(初期費用・固定費)
留意点
- ・法人を設立するには、登記費用(定款認証・登録免許税など)といった初期投資が発生します。・
- ・法人成り後は、赤字や収益が安定しない時期でも、法人としての最低限の税金がかかります。例えば法人住民税の均等割が約7万円発生します。
- ・役員報酬・社会保険料・顧問税理士・会計システムなど、個人事業主時代にはなかったランニングコストが増えるケースがあります。
- ・売上・利益がまだ小さい段階で法人化すると、「手取りが減った」という後悔を招くこともあります。
実務的アドバイス
・法人成りを考えるなら、まず「年間ランニングコスト」を見積もりましょう。例えば法人住民税均等割+社労/税理顧問料+必要な諸経費が発生します。- ・売上・利益がそのコストを十分に支えられるかをシミュレーションしましょう。特に利益が安定していない段階ではタイミングは慎重に検討します。
- ・なぜ法人化が必要なのか、理由を整理しておきましょう。
2. 事務負担・管理負荷
留意点
・法人化すると、個人事業主に比べて求められる手続き・管理業務が格段に増えます。決算書の作成、株主総会・取締役会の議事録、登記内容の変更等。- ・会計・税務・労務の専門性が上がるため、自分で全てを対応するには相当な時間と労力が必要になります。
- ・事務負担が本業の妨げになると、「法人化することで本業に集中できなくなった」「手続きが面倒過ぎる」という声もあります。
- ・事務管理が甘いと、税務・労務リスクが高まります。例えば社会保険加入漏れ、労働保険未手続、登記不備など。
実務的アドバイス
・法人化を決めたら、開業初年度から「事務管理体制」を整えましょう。税理士・社労士の顧問契約を早めに検討しましょう。- ・会計ソフト、労務手続きクラウド、人事・勤怠管理システム等を導入して、生産性が高い環境を構築しましょう。
- ・事務負担を外部に委託するコストと、内部で対応するコスト・時間を比較して、どちらが効率的か検討しましょう。
3. 社会保険(健康保険・厚生年金・労働保険)
留意点
・法人化すると、原則として法人は「健康保険・厚生年金保険」への加入が義務付けられます。- ・社会保険料負担は、役員・従業員・法人それぞれに影響。特に役員報酬を高めに設定すると法人・役員ともに保険料が大きくなり得ます。
- ・社会保険加入手続きを怠ると、未加入が発覚した際に過去最大2年分の保険料を遡って請求されるケースがあります。法人・役員ともにリスクあり。
- ・社会保険料の増加は「固定負担」化するため、利益が少ない段階だと経営を圧迫する要因となります。
実務的アドバイス
・法人化を検討する際、役員報酬の額を慎重に設計しましょう。保険料負担がどのくらいになるか、事前に試算をしましょう。- ・社会保険加入手続きの期限を把握:たとえば、設立後5日以内に「新規適用届」などの提出が必須。
- ・特に従業員を雇用する予定があるなら、労働保険(労災・雇用保険)なども早めにセットアップ。手続き漏れによるトラブルを事前に防止しましょう。
- ・社会保険料が負担になりそうな時期・状況なら、役員報酬を低めにスタートさせる、または法人化を少し先送りする検討もあります。
まとめ:法人化は「タイミング・準備」が鍵
法人化は大きなステップであり、メリットも多いですが「安易に法人化すればよい」というものではありません。むしろ、以下の観点をクリアできるかが成功かどうかの分かれ目です。
・年間コストをカバーできる利益が安定しているか(設立コスト+ランニングコスト)- ・事務・管理体制を構築・運用できる体制があるか
- ・社会保険を含めた負担を把握し、経営を圧迫しない設計になっているか
特に新設法人・小規模法人・これから売上拡大を目指す起業段階では、「利益が出てから法人化を検討する」という慎重戦略も十分有効です。
まずは現状把握をし、本当に法人成り有効かシミュレーションをしましょう。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄