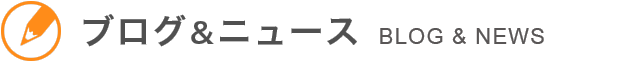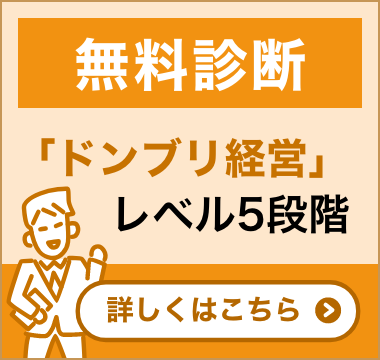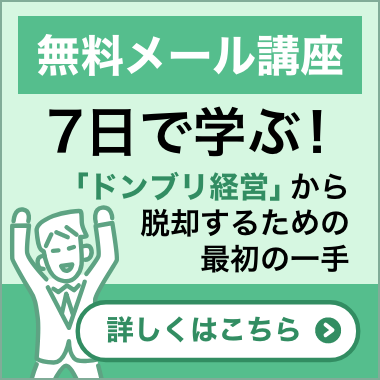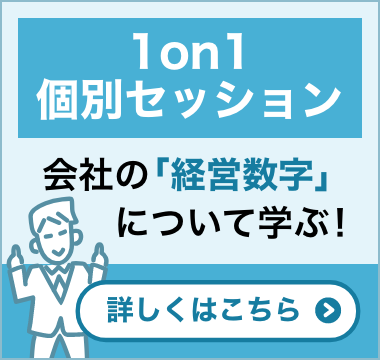2025年10月28日
カテゴリー:
黒字を確保する最初の節目 — 損益分岐点を理解して安定経営へ

365日ブログ
3,011日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
新しく会社を立ち上げた、または新規事業を始めた経営者にとって、
「いくら売上を上げれば黒字化できるのか」は最も気になる数字の一つです。
その目安となるのが“損益分岐点”です。売上と費用がちょうど一致し、利益も損失もゼロとなるポイント。ここを超えると利益が出て、下回ると赤字になります。

1. 損益分岐点とは何か
損益分岐点とは、売上高と総費用(変動費+固定費)がぴったり同じ金額になり、
利益が「ゼロ」になっている売上高または販売数量を指します。
つまり:
・売上高 > 損益分岐点 → 黒字- ・売上高 < 損益分岐点 → 赤字
という構造です。
このポイントを押さえておくことで、「この売上を下回ると赤字になる」というラインを経営者として明確に把握できるようになります。
2. 損益分岐点を構成する費用の区分
損益分岐点を計算するためには、まず「固定費」と「変動費」という2つの費用を区分する必要があります。
・固定費:売上の大小に関係なく発生する費用。例:家賃、人件費(固定給部分)、リース料、固定資産税など。- ・変動費:売上や販売数量に比例して増減する費用。例:原材料費、仕入れコスト、販売手数料、外注費など。
※実務としては、はっきり線引きできない場合があります。その際には方針を決めて進みましょう。
3. 計算方法と具体例
3-1 計算式
損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率
ここで「限界利益率」とは、売上高から変動費を差し引いた金額(=限界利益)が売上高に占める割合です。
3-2 具体例
例えば、月の固定費が30万円、1杯1,000円でラーメンを販売、小麦粉など変動費が1杯あたり200円としましょう。
この場合、変動費率=200円/1,000円=0.2(20%)となり、
限界利益率は0.8(80%)となります。
これを式に当てはめると、
損益分岐点売上高=30万円÷0.8=37.5万円
となります。
つまり、月に売上が37.5万円を超えなければ、この店は赤字という計算になります。
このようなシミュレーションができると、これからどれだけ売上をつくれば「ひとまず赤字脱出」できるのかを定量的に把握できます。
4. なぜ損益分岐点が経営にとって重要なのか
安定的な経営の基礎ラインがわかる
「どれだけ売れば最低限維持できるのか」がわかれば、月次での売上目標設定や資金繰りの目安が定まります。
売上下振れの時のリスクを把握できる
売上が想定より下がった時、「あといくら下がると赤字か」「今の売上は安全域にあるか(安全余裕率)」などがわかります。
商品・サービス単位で収益性を検討できる
限界利益率や変動費率を算出することで、「この商品をもっと売るべきか」「コスト構造を変えるべきか」など判断材料になります。
目標利益達成のための売上逆算が可能
損益分岐点をベースに、「利益〇万円を出すためには売上いくら必要か」が算出できます。
6. 損益分岐点を下げるための具体策
結論は、損益分岐点は下がったほうがより健全な経営になります。
損益分岐点が高すぎると、売上が少し下がっただけで赤字転落のリスクが高まります。
そこで、損益分岐点を下げるための代表的な手段を以下に整理します。
・固定費を減らす:家賃交渉、不要なリース・サブスクリプションの解約、人員構成の見直しなど。- ・変動費率を下げる:仕入れ交渉、原材料の見直し、製造・提供プロセスの効率化、販売手数料の削減など。
- ・限界利益率を改善する:ブランド強化・高付加価値化、マーケットを拡げる、クロスセル・アップセルを活用する。
- 商品・サービスのミックスを変える:限界利益率が高い商品の比率を増やす、低収益商品を見直す。
まずは自社の損益分岐点を把握し、
損益分岐点売上高を下げるために対策を講じていきましょう。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄