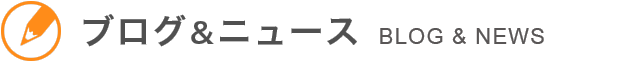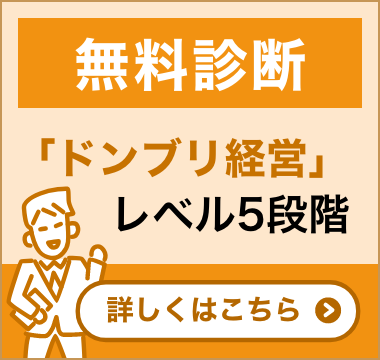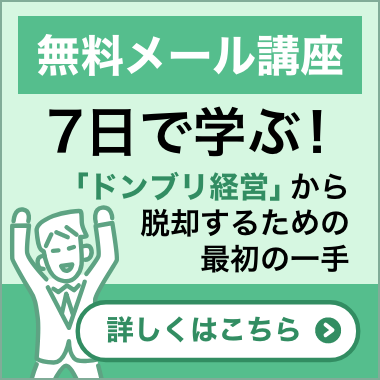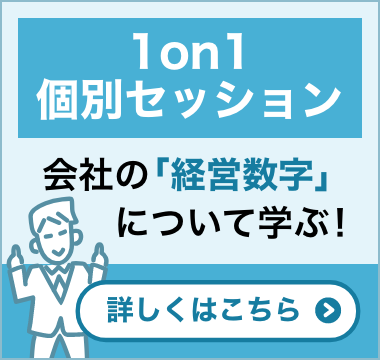2025年8月20日
カテゴリー:
有名企業も導入「賞与の給与化」――経営者が成功に導くための実践ポイント

365日ブログ
2,942日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
賞与の給与化が注目される背景
人手不足や物価高騰の影響により、
企業には「優秀な人材を確保し続けること」と
「安定した給与制度を設計すること」の両立が求められています。
その中で近年注目されているのが「賞与の給与化」です。
これは、従来は夏・冬に一時金として支給していた
賞与(ボーナス)を、毎月の給与に組み込む仕組みを指します。
ソニーやバンダイといった大手企業も導入しており、
中小企業でも検討が進みつつある制度です。
メリット:採用力と安定感の向上
一見すると、賞与の給与化は「社員に安定的な収入を保証する制度」に見えます。
実際、次のようなメリットがあります。
- ・求人媒体でのアピール力強化
月給が高く表示されるため、求職者に「安定している会社」という印象を与えやすくなります。特に30代前後の中途採用層は年収よりも「月々の手取り額」に注目するため、採用強化につながります。 - ・住宅ローンやライフプラン面で有利
金融機関のローン審査では「月収の安定性」が重視されるため、従業員の生活設計を後押しできます。
つまり、採用力と従業員満足度の両面でメリットを得られるのが、この制度の強みです。
デメリット:モチベーション低下のリスク
一方で、実際の運用現場では問題も見えています。
ある中堅メーカーでは、賞与を「夏・冬各2カ月 → 各1カ月」に減らし、
その分を月給に上乗せしました。当初は社員から大きな反発はありませんでした。
初めてのボーナス支給日を迎えると……
- ・「思ったより少ない」
- ・「旅行や大きな買い物に充てられない」
- ・「ご褒美がなくなった感じがする」
といった不満が噴出しました。
人は「年収の合計額」よりも、「体感的な収入の変化」に敏感です。
月給が増えても、一時金が減ると「損をした」と感じやすく、
モチベーション低下を招くリスクがあります。
経営者が取るべき3つの実践ポイント
このような課題を踏まえ、経営者が成功に導くためのポイントは次の3つです。
① 段階的な導入
一気に制度変更すると反発を招きやすいため、2〜3年かけて段階的に移行するのが理想です。
例:初年度は賞与1.5カ月 → 翌年1.2カ月 → 翌々年1カ月
② ハイブリッド型の報酬設計
「完全固定給」ではなく、月給+成果連動型の変動賞与を残すことが有効です。
特に営業部門など、成果が数値で明確に測れる職種では効果的です。
③ 丁寧な説明と対話
説明会を一度開くだけでは不十分です。
管理職を通じた継続的なフィードバックを集め、
社員の本音を把握しながら制度を改善していく姿勢が不可欠です。
まとめ:制度は数字、人は気持ち
「賞与の給与化」は単なる給与制度の変更ではなく、
企業文化や社員の働き方そのものに影響する改革です。
導入の成否を分けるのは、社員が納得して前向きに受け入れられるかどうかです。
経営者が意識すべきは、 制度は数字で作るが、運用は人の気持ちで決まるということです。
社員の立場に立った丁寧な設計と説明を行い、
信頼とモチベーションを守りながら、持続可能な制度運用を目指しましょう。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄