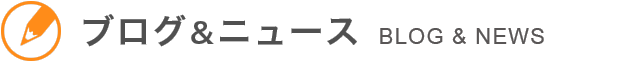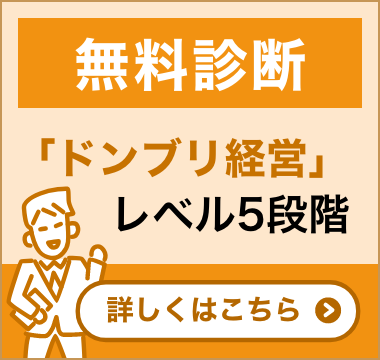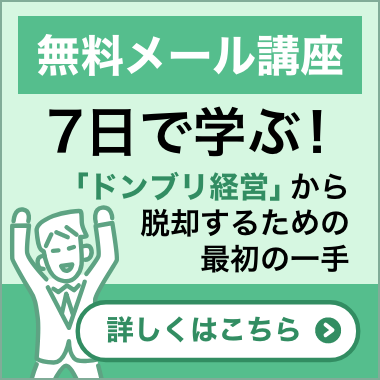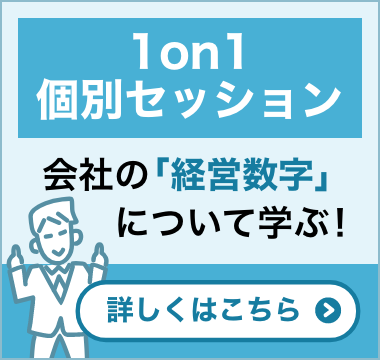2025年9月27日
カテゴリー:
非上場株式と遺留分対策

365日ブログ
2,980日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
中小企業の事業承継では、後継者に自社株式や事業用資産が集中する傾向にあります。
しかし、その一方で相続人の「遺留分」(法律で保障された最低限の取り分)を侵害するリスクが生じます。
対応を誤れば「争族」に発展し、承継どころではなくなるケースも少なくありません。
今回は、非上場株式を承継する際の遺留分リスクと対策を、実務的な視点から整理します。

1. 遺留分侵害額請求のリスク
遺留分を侵害した場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
この請求は金銭で行われるため、後継者は多額の支払いを迫られる可能性があります。
特に、自社株式は換金性が低く、後継者が株式を手放さざるを得ない事態に陥る危険もあります。
2. 経営承継円滑化法の特例活用
こうしたリスクに対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)に基づく民法特例を活用する方法があります。
・推定相続人全員の合意により、贈与株式を遺留分算定の対象から除外できる- ・株式の評価額を合意時点の価額に固定できる
これにより、遺留分争いを未然に防ぎ、後継者に株式を集中させやすくなります。
3. 遺言と遺留分侵害
「遺言で指定すれば大丈夫」と考える方もいますが、注意が必要です。
遺言によって後継者に株式を集中させても、他の相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求を受ける可能性は残ります。
なお、この請求権は相続開始と侵害を知った時から1年間で時効消滅するため、対策を検討する際の目安ともなります。
4. 代償金と生命保険の活用
実務的には、代償金や生命保険を活用した遺留分対策が有効です。
・後継者が承継する資産に換金性がない場合、他の相続人に代償金を支払う仕組みを準備する- ・生命保険金は原則として相続財産に算入されないため、他の相続人への補填資金として活用できる
これにより、相続人間の公平性を確保しつつ、後継者は株式を保持したまま承継できます。
早めの準備で「争族」を防ぐ
非上場株式の承継では、遺留分リスクを軽視できません。
・遺言- ・遺留分侵害額請求に備える
- ・経営承継円滑化法の特例を活用する
- ・代償金、生命保険を組み合わせる
これらを総合的に検討し、相続人全員が納得できる形を整えること。
丁寧な対話が、円滑な事業承継の鍵です。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄