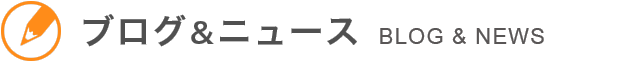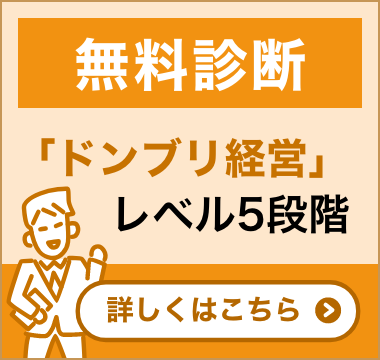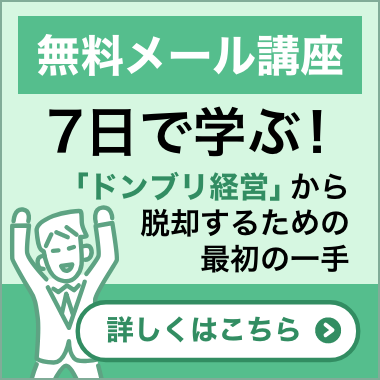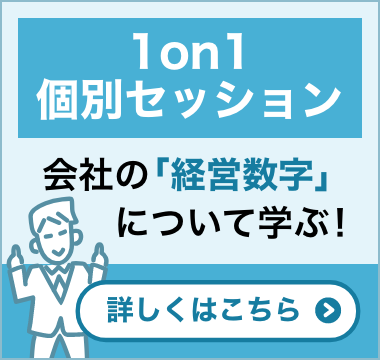2025年10月11日
カテゴリー:
源泉所得税:納期の特例の制度と適用上の注意点

365日ブログ
2,994日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
源泉所得税の毎月納付は、小規模事業者にとって事務負担がかかります。
しかし従業員数が常時10人未満であれば、
「納期の特例」を活用して、半年分を年2回で納付することが可能になります。
本稿では、その制度概要、手続き、メリットおよび注意点を簡潔に整理します。

制度概要
・源泉所得税および復興特別所得税は、原則として支払月の翌月10日までに納付しなければならない。- ・ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収税額を半年に分けて年2回納付できる「納期の特例」が認められている。
- ・特例適用時の納期限は、1月~6月分が7月10日、7月~12月分が翌年1月20日である。1月はやや遅めの期限となる。
適用対象と制限
・特例の対象となる源泉税は、給与・退職金、及び税理士・弁護士等の報酬・料金に関する所得税・復興特別所得税に限られる。- ・原稿料、講演料、広告報酬などは、原則として特例適用外であり、支払月の翌月10日までに納付する必要がある点が注意である。
適用要件と手続き
1.要件
- 給与等の支払を受ける者の数が「常時10人未満」であること。
- 所轄税務署長に「納期の特例の承認を求める申請」を行い、承認を得ること。
2.手続きの流れ
- 申請書には提出時期の制限はない。
- 承認後は、申請の翌々月分の支払分から特例が適用される。
そのため、申請直後は毎月納付になるため、納期特例を開始するタイミングには注意が必要である。
メリットと注意点
メリット
・年12回の納付を年2回に集約でき、納付作業を大幅に簡素化できる。- ・毎月の納付回数を減らすことで、納付忘れなどのリスクを低減できる可能性がある。
注意点
・半年分をまとめて納付するため、1回あたりの納付金額が大きくなる。資金繰りを見誤ると負担になる。- ・納期を超過すると、延滞税および不納付加算税が課される可能性がある。
- ・対象外報酬を誤って特例扱いしてしまうなどの誤処理に注意を要する。
- ・申請月や適用開始月の扱い、また要件逸脱時の切り替え時期のルールを正しく理解しておく必要がある。
「納期の特例」は、小規模事業者にとって魅力的な制度だが、適用可否・資金計画・取扱い範囲を誤るとリスクを伴う可能性があります。
小規模事業者は基本的に適用しているケースが多いですが、
資金繰りを考えて毎月納付にするといった場合も想定されます。
自社の状況から判断しましょう。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄